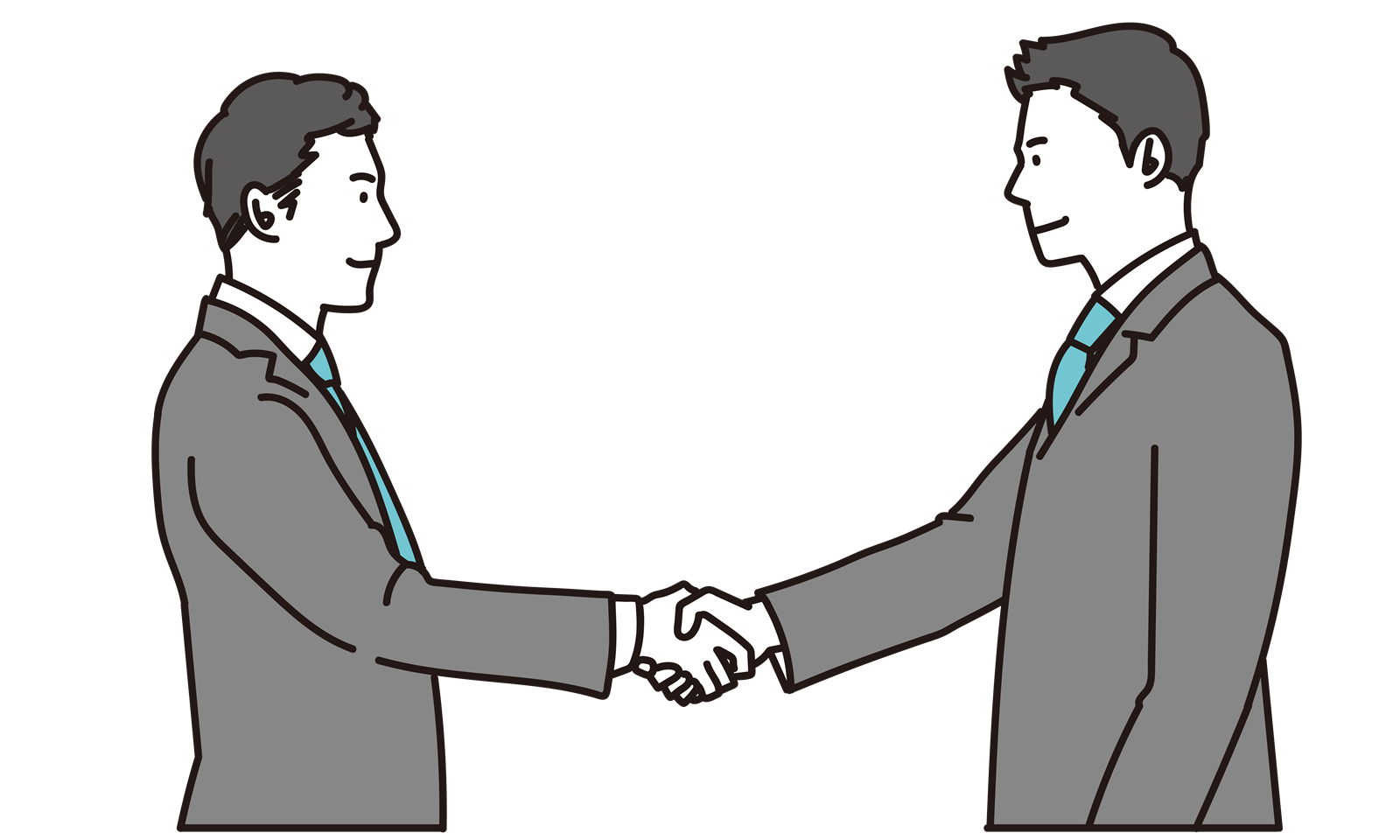江戸時代の公事師から続く日本の弁護士制度の歴史
日本における弁護士の歴史
江戸時代の公事師に始まる弁護士の起源

日本における弁護士の歴史は、江戸時代の公事師(くじし)から始まります。公事師の語源は、「お白州」の最上段の町奉行が座るところを「公事場」と呼んだことに由来すると言われています。公事師は、江戸時代において庶民の訴訟を手助けする訴訟代理人のような存在でしたが、公事師は正式な法的資格や幕府から認められた職業ではないため、裁判の場であるお白州に参加することは出来ませんでした。
多くが町人や浪人の身分で公事宿(くじやど)と呼ばれる施設に居住していました。公事師には悪徳な者も多く、幕府は、公事師の影響によって不必要な訴訟が増えることを懸念しており、公事師の活動をたびたび取り締まっています。特に享保・寛政・天保の改革期には、公事師や公事宿の制限が強化されました。
- 享保4年(1719年):公事師や公事宿の活動を規制し、無用な訴訟の助長を禁止。
- 寛政2年(1790年):公事師の活動が厳しく制限され、訴訟の取次や代理を禁止する通達が出される。
- 天保期(1830年代):さらなる取り締まりが強化され、悪徳公事師が摘発されることが増えた。
公事師は、お白州で直接訴訟代理をすることはできませんでしたが、訴状の作成、訴訟の事前準備、証拠の収集、法的助言などの形で訴訟に関与していました。
具体的には、
- 訴訟当事者のために現在の訴状や準備書面に該当する願書や口上書を代筆する。
- 奉行所での尋問に向けたアドバイスを依頼人に与える。
- 訴訟で有利になるように証拠や証人を手配する。
- 訴訟当事者の付き添いとして奉行所へ同行する(ただし発言は許されなかった)。
明治時代の弁護士制度の発展
明治時代になり、日本では法制度が近代化される中で、1872年に制定された「司法職務定制」によって代言人(だいげんにん)という立場が導入され、公式に認められた職業になりました。 この法令では代言人の他に現在の公証人に当たる証書人、現在の司法書士に該当する代書人が認められました。この法令は、日本の近代的な司法制度の基礎を築く法令です。
これは、江戸時代の「武士による裁判」から、フランスの司法制度を参考に西洋的な司法制度への転換を図るために制定されました。この法令では、司法・行政の分離、裁判所の設置、三審制の導入、代言人の制度化、裁判官・検事の制度化及び拷問の廃止や公開裁判を骨子とする刑罰・裁判手続きの近代化が図られました。
その後、1876年(明治9年)の「代言人規則」によりさらに制度が整備され、国家の許可を受けた者のみが代言人として活動できるようになりました。初期の代言人は、特定の法律教育を受けていなくても認められることがあり、公事師から引き継がれた者も多く存在しましたが、後に司法省の試験に合格する必要があるなど、資格制度が整えられ、法律相談や紛争解決の代理を行う役割を担っていました。
しかし、未だ公事師は信頼が低く、不正な活動を行っていた者もおり、明治初期の代言人の社会的地位は、必ずしも高くなく、「口舌の徒(くぜつのと)」として軽視されることもありました。
代言人の業務内容
代言人の仕事の内容は以下の通り現在の弁護士の仕事と略同じですが、近年の社会構造や経済システムの変化に伴い新たに弁護士の業務として生じたものは含まれていません。
- 訴訟代理行為
民事・刑事の訴訟において依頼人の代理人を務め、法廷で主張を展開しました。特に刑事事件では、被告人の弁護を担当することもありました。 - 法律相談
依頼人からの法律相談を受け、紛争解決の助言を提供しました。 - 契約書の作成・確認
企業、承認及び個人からの依頼により、契約書や法的文書の作成、確認を行いました。 - 交渉・仲裁
訴訟に発展する前に、依頼人の代理として交渉し、和解や仲裁を行うこともありました。
代言人の活躍の場所
代言人の活躍の場所は以下の通りです。
- 裁判所
主な活動の場は各地の裁判所でした。当初は代言人の法廷活動が制限されることもありましたが、徐々にその権限が広がりました。 - 法律事務所
一部の代言人は独立して法律事務所を開設し、依頼人の相談や契約書作成などを行っていました。 - 政界・言論界
明治後期になると、代言人の中には政治家や新聞記者としても活躍する者が現れました。例えば、後に総理大臣となる原敬や、自由民権運動に関与した星亨なども代言人の経歴を持っています。
代言人制度の変遷
1893年に弁護士法(旧々弁護士法)が施行されました。この法律の導入により、試験制度が整備され、弁護士の知識や能力を選抜する仕組みができたのです。この試験の難易度は当時は低かったため、裁判官や検察官よりも低い地位であったと言われています。しかし、時代が進むにつれて弁護士の地位は向上し、現在は基本的人権の擁護や社会正義の実現という使命を持つ職業とされています。
戦後の弁護士制度の変化
弁護士制度の民主化を象徴する大改革
戦後の日本は改革の時代であり、弁護士制度も変化を遂げました。戦後の日本の弁護士制度は、アメリカなどの国の影響を受けながら、独自の進化を遂げてきました。
1949年の弁護士法改正は、日本の弁護士制度において戦後の民主化を象徴する大改革でした。戦前・戦中に国家の強い統制下にあった弁護士制度を改め、弁護士の独立性と自治を確立することが主な目的でした。主な改正点は次の通りです。
日本弁護士連合会(日弁連)の設立(弁護士自治の確立)
- 全国の弁護士が強制加入する「日本弁護士連合会(日弁連)」が創設された。
- 弁護士会が法人格を取得し、弁護士の自治が確立された。
- これにより、国の監督下にあった弁護士団体が独立した自己管理組織へと変わった。
監督権限の変更(司法大臣の権限縮小)
- それまで司法大臣が持っていた弁護士の監督権限が廃止された。
- 弁護士会が懲戒権を持つようになり、自治的な運営が可能となった。
- 国による干渉を排除し、弁護士の独立性を強化する改革であった。
弁護士の資格制度の改革
- 弁護士試補制度を廃止し、司法修習制度が導入された。
- これにより、司法試験合格後、一定期間の司法修習を経て弁護士登録する新たな資格制度が確立された。
弁護士の業務範囲の明確化
- 弁護士の職務範囲が法廷活動だけでなく、法律相談や契約書作成などの幅広い業務に及ぶことが明確に規定された。
- これにより、弁護士の活動がより実務的で幅広いものとなった。
弁護士会の強制加入制度の確立
- 弁護士は所属する地域の弁護士会に強制加入しなければならない制度が導入された。
- これにより、弁護士会の団結力が強まり、弁護士の自治がより確固たるものになった。
新たに弁護士に求められる社会正義の実現
また、社会の変化や法律の発展に伴い、弁護士は公正な裁判や法律相談だけでなく、人権擁護や社会正義の実現にも積極的に取り組むことが求められるようになりました。そのため、弁護士はその職務を誠実に行い、法律制度の改善にも努力する使命を持つこととされています。弁護士には時代の変化に伴い新たに次の使命が求められ、一部については目的に近づきつつあります。
弁護士自治の維持と責任の自覚
- 弁護士会(特に日弁連)による自己規律・自己管理の徹底が求められる。
- 国の監督から独立したことで、弁護士自身が規律を守り、品位を維持する責任が生じた。
市民の権利擁護と人権保護の強化
- 国家権力の濫用を監視し、基本的人権を守る役割がより強調された。
- 戦後の新憲法(日本国憲法)に基づき、憲法訴訟や人権問題に積極的に関与することが期待された。
法律扶助・公益活動の義務化
- 弁護士の社会的責任として、経済的に困窮する人々への法的支援(法律扶助)の充実が求められた。
- 無償の法律支援活動を通じた社会貢献の意識が高まった。
法曹一元化への対応と司法制度改革への関与
- 新弁護士法の下で、弁護士が裁判官・検察官と同等の法曹資格を持つ存在として位置付けられた。
- 法曹一元化(弁護士が裁判官になる制度)の推進に伴い、司法の中核を担う立場としての役割が強化された。
- 司法制度改革や法改正に積極的に関与し、政策提言を行うことが期待された。
専門性の向上と多様な分野への対応
- 戦後の経済成長に伴い、企業法務、知的財産、国際取引、労働問題などの新しい分野への対応が求められた。
- 高度な専門知識の習得や継続的な研修(弁護士の能力向上)が不可欠となった。
市民に対する法教育の推進
- 戦後の民主主義社会において、弁護士は単に訴訟を担当するだけでなく、市民の法的リテラシーを向上させる役割を担うようになった。
- 学校や地域社会での法律教育、法の支配の重要性の啓発活動が求められた。